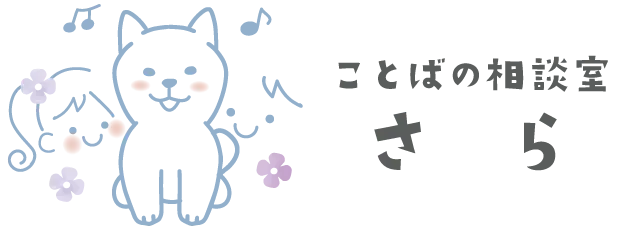言語聴覚士の役割― 私たちができること
「言語聴覚士」という名称を初めて聞く方や、「言葉の相談」で何をするのかわからない方も多いと思います。ここでは、簡単にご説明いたします。
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションに課題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を築けるよう支援する専門職です。また、摂食・えん下(えんげ)の問題にも専門的に対応します。
コミュニケーションの課題には、
- 失語症や高次脳機能障害
- 聴覚障害
- 言葉の発達の遅れ
- 声や発音の障害
など、小児から高齢者まで幅広いケースが含まれます。
言語聴覚士は、これらの問題の本質や発現メカニズムを明らかにするため検査・評価を行い、必要に応じて訓練・指導・助言などを実施します。さらに、医師・歯科医師の指示のもと、えん下訓練や人工内耳の調整も担当します。
医療・介護・福祉・保健・教育など 多岐にわたる領域で、他職種と連携しながら、言葉や聞こえに困りごとを抱える方とご家族を支援する。それが言語聴覚士の役割です。

言語聴覚士不足の現状
- 理学療法士(PT):約21万人(2024年)
- 作業療法士(OT):約12万人(2024年)
- 言語聴覚士(ST):約4.3万人(2025年)
言語聴覚士は毎年 1,700〜2,000人ずつ増えていますが、多くは成人(高齢者)分野へ進むため、小児の成長・発達を支援する言語聴覚士はさらに少数です。しかも、言語聴覚障害やえん下障害など、言語聴覚士を必要とする対象者は約500万〜600万人といわれています。
近年は、医療機関や民間の児童発達支援、放課後等デイサービスなどでも活躍する言語聴覚士が増えていますが、子どものコミュニケーション支援を直接担う人材は依然不足しており、公的機関での言葉の相談は数か月待ちになることも珍しくありません。

「ことばの相談室 さら」を開室しました
こうした状況を踏まえ、民間の相談室という立場を生かし、守秘義務を持つ「言葉の専門職・言語聴覚士」が、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、
- お子さまの言葉の現状を評価
- 状況を整理し、支援方法を検討・実施
が、できる場として 「ことばの相談室 さら」 を開室いたしました。
主な支援内容
- 1歳半健診・3歳児健診後のフォロー、就学前の進路相談、発声の練習・発音の練習(構音訓練)、読み書き支援など言語療法全般に対応
- 遊びを通じた観察や対話を重視し、当日話しきれなかった内容は 後日メールでも受付
- お子さま自身が「自分に合う学び方」を見つけられるよう、ご家族とともに伴走
- 言語聴覚士だけで解決できない場合は、公認心理師・精神保健福祉士・弁護士・税理士など適切な専門職へスムーズに連携
ほかにも、つながることで、できることはたくさんあります。
どうぞ気持ちを楽に、肩の力を抜いて、「ことばの相談室 さら」へお越しください。