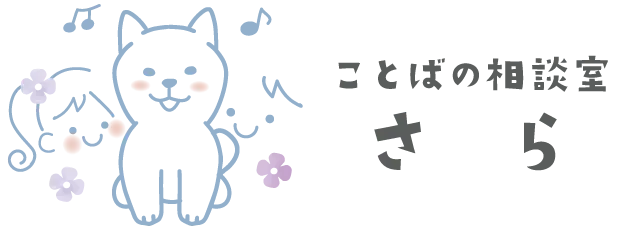「インリアル・アプローチ事典 0歳から使える最強のコミュニケーション指導法」が7月に出版されました。
日本INREAL(インリアル)研究会は、言語やコミュニケーションに障害がある子供たちとのよりよいコミュニケーションを求めて、実践や研究を行っているそうです。
今回、演習形式でグループに分かれて実践的に分析を行う学習会が開かれてましたので、参加してきました。
インリアル・アプローチの姿勢や手法は、ST養成校での小児セラピーの授業でならい、
以後、個別支援の際に心がけている精神的な柱になっています。
本を読んでいて、自分の支援をいろいろと思い返すと、ああすればよかったのかな?
働きかけがどう変わったら、うまくいったのかな?
など、いろいろ疑問に思う点が出てきました。
実際に講座に参加したいと思い探してみましたが、初級講座が終わったばかり。
そこで、9月13日(日)にビデオをみながら実践的に学習する機会があるとのことでした。
実際にどのようにグループで学び合うのか?にとても興味がありましたので、
参加してみることにしました。
自分の見立てと異なる方に、その見立ての理由を実際に聞くことができたり、
答えが1つあるわけではないこと。
グループの中で、いろいろな意見を出し合い、コミュニケーションをとることが大事だということがわかりました。
また、グループをご一緒した先生方と勉強会の内容以外にも、いろいろなお話ができたこと、
今後の学びにつながることができたこともおおきな収穫でした。
(10月のLD学会にも参加してみようと前向きな力をいただきました。現地でもお会いできそうです)
***************************************************
この本を読んだり、勉強会に参加してみて、一人のリハビリ療法士、STとして、
感じたことを書いてみようと思います。
わが子とのコミュニケーションに悩んだり、お子さんとの日々の実践でお困りの保育士さんやSTさんの
ご参考になればと思います。うまくまとまらず冗長になりますが、お許しください。
わたしは、インリアルの姿勢や技法を意識して、お子さんと向き合ってきたつもりでした。
それでも、うまくいかないことがあります。うまくいくことのほうが少ないかもしれません。
コミュニケーション支援は、ほんとうに難しくて、準備したとしても、相手のいることなので、うまくいくとは限りません。
むしろ残念な関わり、あともう少しだった関わりのほうが多い日もあります。そんなときは、落ち込むのは短くして、その場面のメモをできるだけ残すようにしてきました。
ただ、その後の分析が十分にできていませんでした。
読み返すだけで「気を付けよう」と意識するくらいでは不十分でした。
分析が甘いと、子供さんとの関わりを支えるための「あの手この手」が増やせません。
口から適切な関わりのことばが出てこないのです。
具体的に、どんな言い方、どんなタイミングや口調だったら、伝わっただろうか?
とじっくり見つめなおして、メモを書き添えるようにしてから、自分のリハに少しずつ 〇 がつけられるようになり、
お子さまとの個別リハビリに、少しだけ余裕をもって取り組めるようになったように思います。
今回、自分のST4年目くらいからしてきた工夫なのですが、それを思い出して、それが(養成校の授業で練習してきた)インリアル・アプローチの手法だったことに今回、気づくことができました。
実際には、お子からからの開始を「待つ」を意識すればするほど、お子さんが一人黙々と遊ぶ時間が伸びてしまったり、
医療や福祉のリハビリや個別支援は、時間制限があるため、こちらからの誘導しなくちゃならなかったり、、、、。
本当に難しくて、心の中で慌ててしまうこともありました。
コミュニケーションのどの部分で掛け違ってしまったのか?
どういう働きかけだったらよかったのか?
次のよりよい働きかけのため、客観的にみかえすために、ビデオを撮影しておいて、
それをグループでいっしょに見て、検討を重ねていくこと。
それにより、よりよいコミュニケーションにつなげていき、
子どもに、「人とのかかわりの楽しさ」を感じてもらえる手法なのだと感じました。
養成校で学んだときは、ビデオを見る授業もありましたが、毎週小児セラピーという形で実際に目の前で行われるリハビリを観察し、記録をとる練習をしました。
実際にお子さんが遊び・コミュニケーションを開始するところから、どう反応を重ねているのか?を見学させていただいて記録をどんどんとっていく授業でした。
メモを取りながら見るとなると、子どもの反応に偏ったり、大人の反応に偏ったり、よい反応を見逃してしまうことがありました。
見学と記入の同時進行は、私にはとても難しかったように記憶しています。
その都度、見逃した部分を友達の記録と照らし合わせて、友達が漏らさずに子供さんからの発信に気づけていたり、友達の記載や発言を聞いて見落としていた大事なことに気づけることも多かったです。
STになってからは、自分のリハビリは、その方の「飲み方・食べ方・話し方」を短時間撮影して、前後の違いを見て、情報共有に使うことはありましたが、遊び全体を撮影をしておいて、後から1つずつコミュニケーションを見なおしたり、グループで見ていくことは、時間的なゆとりもなくあまりできていませんでした。
その間に、自然と自分のくせのようなものができてしまっていると思いましたので、そこに気づき、変えていくためにも、
ビデオ撮影をして、しっかり保護者様といっしょにやり取りを見返す機会を作っていきたいと思いました。
また、そのビデオをインリアル研究会の先生方に提出をして、スーパーバイズを有料でお願いすることもできるようでした。
そちらについては、ご家庭と相談しながらになりますが、そのような機会を持てることが勉強会に参加することでわかりました。私自身とても安心につながりました。
しっかり本を読み進めたり、インリアル研究会の学びの場にも引き続き参加させていただきながら、
理解を深め、相談室での支援に生かしていきたいと思います。
ことばの相談室さら STのま