みなさま おはようございます。
今日、東京は秋晴れです。
風がとても気持ちよいです。
いくつか前に視覚発達についての勉強会での学びを書きました。
長すぎる記事になってしまいましたので、
こちらに分けて書かせていただくことにしました。
20代のころ、中学生や高校生を塾で教えたり、家庭教師をしていた時期があります。
当時から、学び方が少し違う?と思うお子さんがいました。
「ごめんね、〇と△はどっちがみやすい?」
など「わかる」につながる道筋を聞き取って、いっしょにたどらせてもらえることで、
ようやくそのお子さんの「身に着け方」を教えてもらっていました。(家庭教師の場合のみですが)
自分と学び方が違うのは当然ですが、初めて聞くような(ちょっと遠回りな)学び方だったりしても、そうすることで、知識や知恵としてしっかり身に着くのならと、ひたすらその子に合わせようと思いました。
もちろん無知だったことで、いくつか余計な提案もした記憶もありますが、、、。
これはどうかな?と考えて、教材や便利ツールを作ったり、その子に合わせた教え方を試していきながら、子どもたちの「わかる」を支えるのは、とても楽しい時間でした。
でも、準備にも指導にもとても時間と手間がかかりました。
しかもほんとうに有効なのか、その子に合っているのかどうかもわからないのです。
当時から「わからない」といえないまま育ってきたお子さんにたくさん会ってきて、もっと早い時期に支えてあげられていたら、今もまだ「わからない」と言えないのは辛いだろうな、、、と思っていました。
その時代から学校や塾をはじめたくさんの先生方の研究が重なって、「学習障害」のお子さんの支援が進んでいます。
今、自分はSTとなって、20代の頃と同じように小中学生の学びを支える場にいます。
今は、学習障害とか、ディスレクシアという言葉も、概念も多く知られるようになってきましたが、
私が約30年前にいっしょに学んでいたお子さんたちの辛さや苦しさは、今のお子さんたちにまだあって、ひとりひとり見ていくと、状況はまだそれほど変わっていないのだと感じます。
現場では、お子さんは自分の困りごとをうまく言語化することが難しいです。
また、おひとりずつ困りごとやしんどさがまったく違うので、それらを解消できる学びの形を探していく必要があります。
まず、苦手なことをあぶりだす、検査・評価自体がとても辛いです。
いくつもの評価から引き出した結果から、具体的な方法をためしていくのも(試行錯誤)子どもたちにはとても負担です。
それをきっかけに勉強自体から離れてしまう子どもが出ないよう、伴走する大人もとても気を使うところです。
もともと感覚がたくさん入りすぎて辛かったり(感覚過敏の傾向)、間違えたり失敗したときの経験がトラウマになって不安がでやすかったり、挑戦する気持ちがわいてこなかったり、、、。自信がもてなかったりします。
学校での学びは楽しいこともあったとしても、
刺激が多く、長い時間、座って授業を受ける、次々に課題をさばいていく必要があって、発達面で得意なこと不得意なことの差が大きなお子さんにとっては、そこにいるだけで、本当に疲れきってしまうようです。
そんな話を長く聞いてきましたので、次に出会うお子さんには、できるだけ早く苦しさの原因を探したいと思います。
そのため、こどもの「わかる」を支えるのに伴走する大人は緊張するのだと思います。
私はSTになってから、「読み(書き)がしんどい」お子さんの支援では、ことばの音韻の面で、字と音の結びつきがうまくいかないのかな?と気づけるようになり、その面では支援がとてもしやすくなりました。
これまでの様々な知能検査の結果を参考にさせていただきながら、ことばとコミュニケーションについての検査をとり、いろいろな症例を調べたり、主治医、他のST、心理士さんに聞いたりしながら、そして学校の先生や保育園の先生方と連携しながら支援を続けてきました。
お子さんのテストやノートを見せてもらい、誤り方を分析していくと、「見え方」に課題があると気づきます。その部分は、STの私だけでは捉えにくく、うまく言語化できなかった部分でしたが、「それなら眼科のビジョントレーニングをおすすめする」という対応になっていました。
(もちろん書籍を探して、お伝えはしていますが、家庭での自習を促すのは気が引けました)
そのような場合には、自分はどうしていたかな?
他職種連携型の職場にいたこともあり、保護者の方にはSTができる評価と指導をお伝えし、「見え方」についてはSTは評価や支援が難しいことをお伝えしてきました。
見え方については、学校の特別支援コーディネーター、通級クラスの先生方、主治医の先生にお話ししていただき、評価や訓練につないでいただけるようお伝えすることが多かったです。
ただ、昨年夏、今年の夏と2年連続で「カラフルバード」さん主催の講演会で、井上賞子先生と伊藤陽子先生のお話を伺い、学校現場では「音と文字」、「見え方」とか分けずにとにかく目の前のお子さんの支援をどんどん続けていらっしゃることを教わりました
私は、音韻ルートの評価ができるようになった。
次はわたしもとにかく「見え方」も学ぼうと思いました。
(実際には、音韻だけ、見え方だけというお子さんは少なくて、音韻の課題と見え方の課題の両方かな?、ほかにも何かあるような・・・というケースも多いと感じます)
相談室として開業したわけですから、相談室さらに来てくださる方に読み書きの評価をする際に、
「見え方」についても(評価は専門外なのでできないとしても)しっかりと知識をもって関わることが大事だと思うようになりました。
そこで、今回、視覚発達についての勉強会に参加させていただきました。
10月にはLD学会に参加してきます。
11月にはまた井上賞子先生と教え子の方との講演会に参加させていただきます。
こちらのブログでもご紹介させていただきたいと思います。
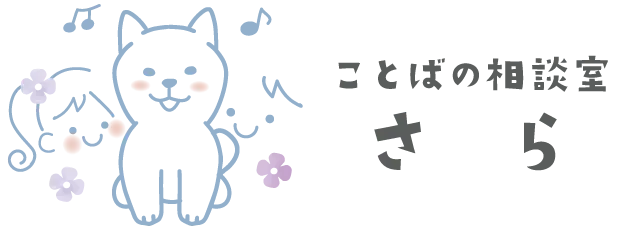
コメントを残す